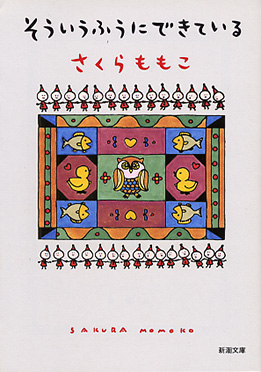その電車が銀河鉄道に変わるとき

電車に乗っているとき、ずっとこのまま居られたらと思うことがある。そう思わせる車両がたまにある。
他人の気配や視線というのは緊張をもたらすものだけど、不思議なくらいそれが無い車両なのだ。他人同士が絶妙な空気感で配置されていて、誰も各人をじろじろと眺めたり、詮索したりしない。大きな声でゴシップを話す人もいない。前髪の脂ぎった、いちゃいちゃの激しいカップルもいない。舌打ちをするおじさんもいない。ただそれぞれが、他人との境界線をふんわりと守っている。そして自分が誰であるかを忘れているかのような、ゆるみ切った表情をしている。ぼーっと、安定感のあるラクダに乗って砂漠を旅しているかのような表情。みんなが車両のその空気に包まれることによって、ようやく自分の輪郭というものを手にしているかのような、そんな感じである。
会社では高い役職をもっている人でも、はたまたフリーターであっても、ただまんだらけに行ってきたニートの人であっても、さっきまで会社で後輩をいびっていた女性社員であっても、育児が本気でめんどくさくなってきている主婦の人であっても、実は25世紀から来ている人であっても、それはその車両では何も意味をなさない。ただ「そこにいる人」としてただそこにいるのみである。そのときわたしも何者でもない。
そういうとき、自分に起こったすべてのことがとても遠く感じる。今朝床に落ちてるコーヒー豆を虫だと思って一人でビビり倒したこと、原宿で知らない人に頼まれて写真を撮ったこと、親族に莫大な借金があったこと、足の小指の爪が割れたこと、恋人からもらった手紙が素晴らしかったこと、生まれたこと。スケール大小のさまざまな出来事が自分から切り離されて遠くに行き、どれも等しく極小になる。なんの星座も作らないカスのような星になる。
その車両にいるわたしは同じ身体で体験してきたすべてのことを自分のことだと思えない。「女子大生」「アルバイト」「○○さん」「○○ちゃん」「年齢オブジョイトイさん」、すべての肩書きがはぎ取られてただのそこにいる人でしかない。それはまわりの他人も同じである。こんな車両にいて、課長でいられるわけがない。
そしてそれはびっくりするほど心地いい。
この社会では一貫した「自分」を持たないとやってられないのだと思う。でもそれはすごくキッツい。
「積み上げてきた経験」とか、「あの頃の自分がいたから今の自分がある」とか、情熱的な人は言う。彼らの人生というか成長物語は、切る度に顔がイケメンになっていく金太郎飴のようなものである。同じ顔ではあるけど、徐々にアハ体験的にイケメンになっていく。確実に成長していく。一貫した「自分」をもっている、あるいはもっていると思っているひとにはこうした成長があるのだ。
一方でわたしの人生は切っても切っても同じ顔が出てこない金太郎飴のようなものなのだと思う。その細長い飴は自分のこの身体だとして、それは揺るぎなくいつも在るんだけど、切ったときに出現する顔はいつも違う。カニエ・ウェストが出たあとに数千回切ると岡本夏生などが出てくるかもしれない。さっき考えていたことがもうつまらない。さっき嫌いだったことがもうおもしろい。さっきやっていたことも明日やるとは限らない。よって成長はない。
そんなめちゃくちゃで怠惰な金太郎飴でも、切られずに、断片を見せずにそのままゴロンと存在していられるのがそんな車両なのである。ここにいる誰も、わたしの断片を知らない。興味もない。見せる必要もない。だから心地いい。そして無数に存在する自分のあらゆる顔なんて、心底どうでもいい。どれもみんな遠く感じる。どうせ薄っすいスライスの顔である。
ほら、みんな円柱型の色とりどりの金太郎飴に見えてきた。金太郎飴が座ったり、つり革につかまったりしている。切ればどんな顔が出てくるかをお互い探り合おうともしない。
あれ、これってみんな死んでるんじゃない?ひょっとしてこれ、銀河鉄道なんじゃない?わたしの地元のセンパイ、宮沢賢治は「死者しか乗れない列車が銀河空間を縦横無尽に旅する」というぶっ飛び設定を100年前に思いついた変態の人なんだけど、センパイがいってたやつってこれなんすかね。
目黒線の元住吉と武蔵小杉の間に差し掛かると、グッとレールの高さが上がって電車が浮き上がるような感覚がする場所がある。このときわたしは「いよいよ離陸か?????」と思う。社会から隔離された金太郎飴たちを乗せて、東急目黒線は夕焼けの空に飛び立ち、銀河空間へ飛び出していく。ああもう街の灯りがあんなに遠くまで。もうずっとこのまま居られたら。
「○○ステーション、○○ステーション」
わたしは黙って電車を降りる。
父という名の野性

「ちょっと川の様子見てくる」
死亡フラグとして名高いこのセリフ、うちの父親は実際に言った。(ふつうに生きている)
毎年台風が来ると、川の様子を見に行って転落して死ぬ人がいる。こちらとしてはなぜそんなに川が気になるのか不思議でしょうがないけど、彼らからしたら何か抗いがたい衝動に導かれて川へ足が向かうのだ。
――川に行かなければいけない。川へ行きなさい。
それは野性の衝動とでもいうべきか。
小さい頃、大型台風のなか川の様子を見に行くと言った父を母と一緒に止めた。我が子の手を振り払い、父は愛車のダークグリーンのエスクードに乗って消えた。窓にはビタビタと雨が打ち付けていた。「お父さん死ぬかもな…」と思った。
結局父は生きて帰ってきた。母やわたしは「台風のときに川の様子を見に行く人はおかしい」と小言を言った。すると普段縄文土器のように無口な父は、顔をぐにゃりと歪めて聞いたことのないくらいの大声で怒鳴った。
「アユ釣りの下見に行ったんだ!!!!口出しするな!!!!!!俺にかまうな!!!!!!」
あまりに怖かった。父の顔が崩壊して、縄文土器のするどい破片がこちらへ飛んでくるような感じがした。父に自然が乗り移ったんだと思った。
穏やかな気候と恵みをもたらしてくれる自然に安心しきり、未曾有の天災が起こればその凄まじい威力におののく。そして天災が過ぎ去れば、あの恐ろしさを忘れ、ふたたび安心しきってしまう。わたしの父への距離は、ちょうど自然との距離のようだった。
わたしはいつでも安心して生きていた。でもその安心を、父はときどき壊しに来た。
父は野菜でもフルーツでも魚でもとにかく旬の新鮮なものを、まるごと食べるのが好きだった。夏はとうもろこしやトマト、秋はぶどうやゆでた栗、冬はワカサギ、春はなんだっけ。たまに大きな肉の塊を燻製にして食べさせてくれた。わたしは父の食へのワイルドなこだわりが好きだった。小さい頃はとくに「食べ物をまるかじりする」ということを最高にかっこいいことだと思っていたので、ウッドデッキで父の横に座って汁を滴らせながらプラムやトマトを食べ、近所の友達に見せつけていた。父はそんなわたしに「お前は食への好みが俺と似ている」と満足そうだった。
しかし、父の食へのワイルドなこだわりは行き過ぎていた。
その日は山奥にある父の実家へ向かっていた。うっそうと茂る木々の中を、いくつものカーブを超えて登っていく。わたしは、結構スピードを出しながらも器用にカーブを曲がる父の運転に安心しきってくつろいでいた。すると父がいきなり「あっ、アレは…!!!」と言って、急に車を止め外に出たかと思うと、ものすごい勢いでガードレールの向こうの木に登り始めた。落ちたら死ぬ高さの木に、ためらいなく登り始めた。
怖かった。やっぱり父は命知らずだった。母が悲鳴を上げた。
木はあまり頼りがいのあるものではなさそうで、しなっている。父はそこにしがみつき、なにやら懸命に別の木に手を伸ばしている。
しばらく格闘したあと、父は心底くやしそうに戻ってきた。
「サルナシの実を、おまえたちに食べさせたかった…」
キウイフルーツの野生種ともいわれるサルナシは、稀少性が高く幻のフルーツと呼ばれている。父はその実をものすごい動体視力で発見し、わたしたちに食べさせようと命知らずの木登りをしたのだ。これは、人間の親子の在り方なんだろうか。つがいに必死で木の実を運ぶ野性の鳥のようではないか。
母曰く、つき合っているときからサルナシの実を食べさせようと木に登りだすことがあったらしい。しかし、これほどの危険を冒したのは初めてだったとも言っていた。わたしはあまりに濃い父の野性を目の当たりにして、足がすくむようだった。
そのほか、父はあらゆる衝撃体験をわたしたちにもたらした。
ある日、「クワガタを採るぞ!」と張り切る兄とわたしを、父はエスクードに乗せて湿った雑木林に連れていった。
林に入ると、なんだか違和感を覚えた。そこかしこが茶色いモザイクのように見えた。木々の緑は上に遠く、わたしと兄は落ち葉のようなものを蹴りながら進んだ。
「おとーさーん、ほんとにクワガタいるー?」
「いるんじゃーないか?」父は後ろから言った。
するとそのときボタボタボタッと何かが上から降ってきた。わたしたちの前に、腐って茶色くなったバナナのようなものが五つ六つ転がった。わたしたちは足を止めた。
よく見るとバナナはうねうねと動いていた。それは木々の養分を吸って育った、巨大なナメクジだった。ナメクジは高いところから落ちた衝撃で、腹をみせながらのたうち回っていた。
クワガタを採りたかっただけの幼い兄妹は泣き叫んだ。
あたりを見回すと、茶色いモザイクのようにみえていたものは全てナメクジだった。落ち葉のようにみえていたものもナメクジだった。そこかしこで隙間なく呆れるほど大きいナメクジがうごめいていた。そこはナメクジの森だった。
わたしと兄の泣き叫ぶ声が、木々にこだました。その声に反応するかのように、上からはナメクジが降り注いだ。こんなときこそ頼りにしたいのが父親である。父の方を振り向いてみると、
見たことないくらい笑っていた。
降り注ぐナメクジ、地面でのたうち回るナメクジ、木の幹でうごめくナメクジ。萩原朔太郎がこの光景に出会っていたら「竹」を「ナメクジ」に差し替えていただろう。そんな地獄絵図の中で父は笑っていた。水を得た魚のように、肉を得た獣のように。悲鳴と笑い声が共鳴するナメクジの森であった。
父はそばにある木を揺すった。するとおびただしい量のナメクジが降ってきた。「お前らもっとちゃんと粘着しろよ!」と今なら思えるけど、本当に心臓が止まるほど怖くてそれ以降の記憶がほとんどない。父が何を思ってわたしたちをナメクジの森に連れていったのか、今となっては謎に包まれている。
またあるとき「川に連れていく」と言われ、兄と一緒に無邪気についていった。季節は覚えていない。
連れていかれたのは岩のようなものに挟まれた、そこそこ大きな川だった。「なんか中国っぽい」と思った記憶がある。わたしと兄は水辺が好きなガキだったので、はしゃいで石を投げたり、水をパシャパシャして遊んでいた。
すると父が「あれ見ろ!!!」とうれしそうに叫んで呼び寄せた。隣に並んで川の上流を見たわたしたちは、目を疑った。
何十組ものカエルのカップルが、葉っぱに乗っかって交尾しながら流れてくる。カエルは見たところ拳くらい大きく、茶色くよどんだ色をしていた。そんなカエルが二匹重なって、おんぶみたいになっている。それが何十組も、しかも葉っぱに乗っている。カエルの間でそういうファックが流行っていたのだろうか。時々川の流れに翻弄されて、くるくると回ったりなんかしながら押し寄せてくる。壮観だった。
そのときはもう怖いというより、圧倒された。わたしたちの知らないところで、自然のなかでは本当に驚くような光景が繰り広げられているのである。父はそれをわたしたちに見せたかったのだろうか。
父によってもたらされた衝撃的な体験を回想してみた。あまりにぶっ飛んだ内容なので、自分の記憶に自信が持てていなかったんだけど、この間兄に聞いてみたら「それは全部本当にあったことだよ」と言われ、改めて鳥肌が立った。父はやはり自然そのもののようである。こうしてときどき恐ろしさを思い知らされる。
ただ、これを読んだ皆さんに言いたいのは、「ヤマナメクジ」で検索してはいけないということのみである。
ダイエー横浜西口店セルフレジの躁うつ感について

今はどうなのかわからないけど、横浜駅西口にあるダイエーのセルフレジのテンションが独特だったことを思い出した。
たいてい、セルフレジとは元気の良いものだ。どこかのいい声をしたお姉さんが「商品をスキャンしてください♪」と言ってくれる。セルフレジ用の声優さんとかいるんだろうか。わたしの知らない世界である。
なにはともあれ、ダイエー横浜西口店のセルフレジ音声は一味違う。レジ袋をセットし、お会計ボタンを押すとまずこうスタートする。
「いらっしゃいませ(ボソッ」
エッ?と思う。今なんつった??
このセルフレジ音声の暗さをなんと形容すればいいのか、わたしのボキャブラリーの薄さを憎むばかりだけど、とにかく陰気なのである。絶対にAmazarashiとか聴いてるでしょ、と思うような憂いを含んだテンションである。なんだこいつ大丈夫かと不安になってくる。
しかししばらくすると様子が変わってくる。
「商品のバーコードをガラス面に近づけてください(^^♪ バーコードのついていない商品は」などとご機嫌でのたまう。
声もいきなり変わる。さっきまでの陰気な鬱ボイスはどこに消えたんだ。わたしはさっきまでのおまえの方が友達になれそうな気がしていたよ。声も10歳は若返ったような感じで、ものすごく気分よさそうに指示を出してくる。完全に別人の声である。パン屋さんで働いていたとき、「とりあえずいらっしゃいませだけ元気に言ってくれたら最初は大丈夫だから」とアドバイスされたものだったが、こいつはまったくの逆。いらっしゃいませは陰気なのに、レジ打ちは元気いっぱいなサイコ店員である。
そしてその後意思疎通が難しくなっていく。
「商品をスキャンしてく…ヒャク…ナナジュウ…二……エン⤵商品を袋に入れ…ヒャク…ヨンジュウ…ハチ……」
次々に食い気味で指示を出してくるうえに、金額を言うところだけカタコト。怖い、怖いっす。あ、なんか今ベラベラしゃべりたい状態になってるのかなと思う。それでも最後はテンション高い状態で送り出してくれるし、「忘れ物はないか?」と親切にも聞いてくれる。
「ありがとうございました(^^♪」
という声を聞き、「調子が良さそうで何よりだわ…」と思いながらレジを去る。
しかしやつはまた次の客に言う。
「いらっしゃいませ(ボソッ)」
朝7時から夜11時まで、休みなくテンションを上げ下げしているダイエー横浜駅西口のセルフレジ。どうか皆さんご声援を。
年齢オブジョイトイという暇なハガキ職人みたいな名前が生まれた背景

年齢オブジョイトイという滑り気味のハガキ職人のような名前でブログを始めて、二ヶ月ちょっとになる。この名前、ダサくて意味不明だけど気に入っている。
ハガキ職人の考える名前って、「どうにかこの世に一つのシュールな名前が欲しい!」という切実さに満ちていて好きだ。彼らは同じ切実さを持つばっかりに、似たような名前になってしまう。まず考えられるのは、「サイケデリック神社」とか、「酒粕ファンタジア」とか、カタカナ語と熟語を無意味につなぎ合わせたおもしろ風の名前である(これには年齢オブジョイトイも属している)。それか日本によくある苗字を無意味に使った、「ピューと吹く小松」とか「凛として三船」などもありそうである。あとは「おかゆは飲み物」とか「はと飛ぶゆうべ」などのほのぼのシュール系など。この世にペンネームは数あれど、ハガキ職人の名前の大半はざっくりと類型化できそうである。
「この世に一つのシュールな名前」を求めて、一生懸命考えて、たどり着くのは似たり寄ったりの滑り気味なペンネーム。そのどんぐりの背比べのなかで他人から笑いを取るのは難しい。たまにペンネームだけでおもしろいひとがいるけど、あれはすごいことなのだ。
こうなればもう自分で満足していればいいではないかと思う。わたしは年齢オブジョイトイに満足している。というのもこれは、わたしをかつて大爆笑させた言葉だからだ。
その夜、わたしは親友の部屋で飲んでいた。そこにはわたし(前髪が長い女。よく「奥さん」と話しかけられるのが悩み。)と親友のパン祭り(前髪の長い女。酔っぱらうと「コミケに出店してみたい」というささやかな夢を語りだす。)と、わたしの高校時代の後輩の根暗モグラ(前髪の長いバンドマン。顔が大きく、服装がダサい女が好き。)が居た。この三人で飲んでいると、楽しいは楽しいけどあまり明るい話はなかった。「うまく行かない人は、前髪を切りなさい」みたいな啓発本がそろそろ書かれてもいいのではないかと思った。
みんなてんでばらばらのことをボヤボヤとしゃべっていた。パン祭りは好きなゲームのせないずみという推しキャラについて語りだし、頼んでもいないのに押し入れからグッズを引っ張り出していた。わたしは「歯ブラシにも、キモい歯ブラシとキモくない歯ブラシがある」という意味不明の話をしていた(わたしの思うキモい歯ブラシ
http://www.cainz.com/shop/g/g4901221819609/ただし磨き心地はめちゃくちゃいい)。根暗モグラは何を言っていたか覚えていない。調布に住んでいることは覚えている。
そんな各人が好き勝手に思いついたことを口にするまとまりのない空間で、互いの顔を見ることも忘れていたけど、ふとパン祭りの方を見ると妙なポージングをしていた。M字開脚をするようにしゃがみ、首をふくろうのようにもたげ、「uh-huh?」みたいな表情をしてこちらを見ていた。そのアーハンの表情と、見事なM字開脚が面白くて、「なんかインリン・オブ・ジョイトイみたいw」とろれつの回らない口調でつまらない事を言った。するとアーハン?の表情のまま「ハァ?年齢オブジョイトイってなんだよ」とつぶやくように言った。もう誰も会話をする能力を持っていなかったのだ。
でもなぜか1秒後には全員が「年齢オブジョイトイ」という言葉に爆笑していた。「なんだよそれ笑」と、思考停止の三人はまるでそれしか知らないかのように笑い続けていた。出口を失った感情をすべて「年齢オブジョイトイ」という、偶然発生した謎の言葉が吸収していた。みんな「いや、年齢オブジョイトイって何だよ!」と言っていれば、交わっていられるような気がしていた。わたしは年齢オブジョイトイをブログか何かのペンネームにしていいかと、パン祭りに許可を求めた。パン祭りも「忘れないように書いとけよ」と紙切れを渡してきて、それに汚い字で「年齢オブジョイトイ」と書いた。
翌朝、ポケモンかなにかのぬいぐるみを抱いて寝ているパン祭りにそっと別れを告げ、根暗モグラとわたしは駅まで歩いた。最悪の口内環境を和らげるため、コンビニに寄り各自お茶やガムなどを買った。駅に着くと、根暗モグラとは反対方向の電車に乗った。昨日あんなに笑ったのがまぼろしのようだった。
ガムの包み紙を探してポケットに手を突っ込むと、ボロボロになった紙切れが出てきた。「年齢オブジョイトイ」と書かれてあった。たしかにあの部屋で笑っていたのだ。あんなにおもしろかったのに、翌朝にはこんなにおもしろくなくなるなんて。さみしいなあと思った。でもペンネームにするって決めたのだからちゃんと使おうと自分に誓った。
今はなんだかんだ「年齢オブジョイトイ」を気に入っている。おもしろいとかではなく、なんか良い感じだと思えてくる。言葉って、発した直後は「すっごいイカすこと言った」と思っていても、少し経つと「さっきのダサかったな」と恥ずかしくなり、また時間がたつと「まあまあ良かったかも」と思えるようになる。そしてブログに書いてる日記もそうなのである。その一瞬恥ずかしくなる段階のときに、勢い余って消したりなんかするとあとで「やっぱ結構よかったかも…」と思えてきてしまうのだ。だからどんなめちゃくちゃなことでもちゃんと残しておこうと思う。「年齢オブジョイトイ」も変えないでおこう。
覚醒・暴れメガネ★★★★★

朝、ゴミ出しをしたついでに近所を散歩していた。前住んでいたところと違い、ほどよく人がいてにぎわっており歩きがいがある。そのときのわたしは、筒みたいなまっすぐなワンピースにサンダル、家用にしているウディ・アレンみたいな変なメガネをかけた近所仕様だった。たまにそんな恰好でスーパーに行くと、不動産のひとが勧誘してきたりする。わたしとしては「よくこんな金のなさそうな人に声かけるな…」と思っている。
そんなくたびれたマダムスタイルでなだらかな坂道をゆっくり下っていると、向こうから小さい男の子が母親に手をひかれて歩いてくる。嬉しそうに母親の方を見上げ、あれがあるよこれがあるよと報告しているようだ。電柱やコンビニを指さしては、何事かを元気にしゃべっている。母親もやわらかい笑顔で見おろしている。幸せそうな、ほほえましい親子だ。
親子とわたしがすれ違う直前、男の子がニコッと笑ってこちらを見た。わたしも思わず癒され、あら何かしらと微笑んでそちらを見た。
そして男の子が言った。
「暴れメガネ」
え、何ですか?パードゥン??パードゥンパードゥンパードゥン???
それも母親への報告だったようだ。おそらく視界に入れたものを全部言葉にして報告しているのだ。だとすればこのわたしは「暴れメガネ」で間違いない。一瞬でもほほえましい親子だと思って和んだのが間違いだった。
たしかにメガネはかけている。悪いか。近所に出るときくらいコンタクトじゃなくてもいいだろう。しかし「暴れ」とは何だ。すれ違うその刹那に、どんだけ人の内面に踏み込んでくるんだ。何、本人も自覚していない潜在的な特性に言及してくれてるんだ。わたしのどこが暴れてるんだ。わたしの何がわかる。いや、この日を待っていた気がする。ずっと自分の置かれた居場所に違和感を感じてきた。メガネをかけると、その重みとともに自分のなかの抑えきれない凶暴な衝動が湧きあがるのをどこかで感じていた。いま、その力を開放するときなのかもしれない。
謎の透視能力をもった少年に、すれ違いざまに名づけられたわたしはそのとき「暴れメガネ」として覚醒した。このメガネの中に、もうあなたは映らない。もう誰も、わたしを止められない・・・。
こんな妄想をしながら家まで歩いた。
鏡に映ったわたしはやつれメガネで、まったく迫力がなかった。そして男の子は「暴れメガネ」ではなく「アラレメガネ」と言ったのだと気が付いた。
昔ながらの銭湯って、番台から裸丸見えなんですね
超絶レトロな銭湯、太平館
今日は兄が「下町のレトロな銭湯に行きたい。アッツアツの黒湯がいい。」と言ったので、少しだけ足をのばして太平館に行ってきた。

いや、本当に昭和で時止まってた。
まず玄関で靴を脱ぎ、木札を抜き差しするタイプの靴箱にいれる。
すると、そこですでに男女ふたまたに別れ、両サイドから番台に接することとなる。大人ひとり470円。そっけなくお金のやり取りをしてくれる眠そうなじいさん。「まいど」と言われ、一歩足を踏み入れる。
さて、脱衣所はどこでしょうとあたりを見回すと
そこはすでに脱衣所であった。

番台のもとから歩くこと一秒、もうそこは脱衣所であった。番台からはもちろんがっつり丸見えである。じいさんはほぼ寝ているような、究極の省エネ状態にあったけど、それにしてもちょっと気になってしまう。
「え???」と思って立ち止まっていると、後ろから来た婆さんがザッと豪快に服を脱ぎ始めた。負けてられるか、ということでわたしもバッと服を脱いだ。何十年も銭湯を守り続けている番台にとって、裸体など塵ほこりのようなものだろう。
思いがけない昭和の洗礼を受け、ひとつ大人になった。
そしてお風呂も昭和そのものだった。
まずもってシャワーの湯がとんでもなく熱い。わたしは「ダァァ!アツッ」と叫びながら、わしわしと髪を洗った。横ではどこかのおしゃまなガキんちょがケケケと笑っていた。途中からは「ケロリン」と書いた風呂おけで、水と湯をちょうどいい塩梅でブレンドして溜めて、それで体や頭を流していた。「なんて玄人向けなんだッ…」と興奮しながら、体を熱湯で赤くしつつ洗い終えた。
そして肝心の湯。
どす黒かった。魔女が煮立てているせんじ薬のような液体が、ぶくぶくと泡を立てている。すこし面食らうけど、銭湯好きの間では評判の名湯らしい。
片足を突っ込むと、Wow、アッツい。
ゆっくり茹で上がって身がほくほくになりそうなアツさ。
隣で小さいガキんちょも平気そうにつかっているので、なんとなく意地になってつかる。しかし肩までつかると慣れてくるもんで、気持ちよくなってくる。内側から身体が温まって、肩甲骨あたりの張った感じも和らいだ。この黒い湯、おそらく肌にめちゃんこいい。少しざらついていた二の腕がすべすべしてきた。
隣は銭湯の定番、ジェットバス。絶妙にツボを刺激してくる。足の裏、ふくらはぎの裏、腰の下の方、肩甲骨の埋まりがちな部分。それらに勢いよく湯が押し当てられる。思わず「あぁ~~」と声が出る。ガキんちょもなぜか真似して隣に来る。
しかし毎回疑問なんだけど、なんでこのジェットバスはこんなに身体がかゆくなるんだ。血行がよくなるから?角質が落ちるから?とにかくわからないが、このジェットバス痒い問題は、あきらかに回転率に貢献している。どんなに好きでも長時間はできない。
ああもう死ぬというとことまで湯につかり、ケロリンに溜めた水を頭からかぶる。
ッカァ~~~~~~!!!!!
最高に気持ちいい。これをするために生まれて来たんだろうかと思う。
風呂を上がると、びっくりするほどレトロな道具たちが出迎える。最初は番台から丸見えなことに気をとられていたけど、一回10円のツボ押しマッサージとか、えんじ色のけんすいをやる器具とか、パーマかけるときみたいな髪乾かし機(おかまドライヤーと呼ぶそうです)とか、とにかくすごい。ガキんちょと競い合うようにして懸垂をしてきた。わたしはこのあとビールを飲むんだぞと心のなかでガキんちょに自慢する。
髪もろくにかわかさずに番台のじいさんに「どうも」と言って外に出ると、風が優しい。兄はシャンプーを忘れ、30円で花王のホワイト石鹸を買って頭からつま先まで洗ったらしい。それもまた銭湯。
外に出ると、さっきの空間はいったい何だったんだと不思議な心持ち。
変わらずにあってほしい、昭和の名湯太平館。
Nissyこと西島隆弘さんの黒い乳首を前にしながら、クレープを粛々と売るお姉さん
ある日、渋谷駅が茶褐色だった。よく見るとそれはNissyの裸体だった。
![特別付録DVD付 anan (アンアン)2018/08/15・22 No.2114[愛とSEX] 特別付録DVD付 anan (アンアン)2018/08/15・22 No.2114[愛とSEX]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41hiBIMRIKL._SL160_.jpg)
特別付録DVD付 anan (アンアン)2018/08/15・22 No.2114[愛とSEX]
- 出版社/メーカー: マガジンハウス
- 発売日: 2018/08/08
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログ (1件) を見る
いつも何かしらの広告がジャックしている、渋谷ちかみちの柱群。
その日はAAAのNissyがanan「SEX特集」で見せたヌードが一面を飾っていたのだ。大樹のような柱が、ものすごく近い感覚で並んでいて、そこにはNissyのあんな姿やこんな姿が映し出されている。暴力的なセクシーゲリラ。
麗しい外国人女性に今まさにKissしようとするNissyのぽってりとしたコーヒー豆のような唇、茶褐色に焼けた肌、女性と絡みながらもなやましげにこちらを見据えてくる眼差し、あるかなきかのわき毛。なんの心構えもない状態で、いきなりセクシー写真を目の前バーンと差し出されてしまい、どんな顔でそこを通ればいいのかと戸惑ってしまった。
とっさに「あっ、すみません」と思った。
強制的に見せられているにも関わらず、なんかすんませんという気持ちになった。
ほかの人も微妙に心をかき乱されているのか、いつもの雑踏がすこしだけランダムな動きをしているように思えた。まるでコソ泥のような速さで、写真を撮影している妙齢のマダムもいた。
Nissyのヌードは地下道に燦然と輝き、道行く人々の心の中にほんの少しのうしろめたさを植え付けていた。
何よりうしろめたさを刺激しているのは、Nissyの茶褐色の身体にぽつねんと出現している、真っ黒な乳首であった。
男性の乳首はそもそも「見えていいもの」として取り扱われている。男性が上半身裸でうろうろしていても、あまり気にならない。しかしそれは乳首が存在感を放たない場合である。通常男性の乳首は「あってないようなもの」として扱われている。だからわたしたちは男性が上半身裸でいても乳首を注視することもないし、なんらうしろめたい気持ちを抱くこともない。
しかしNissyのそれは強烈な違和感を放ち、ブラックホールのようにわたしたちの視線を吸い寄せた。そしていくばくかのうしろめたさと、「み、見てねぇし!」という誰にするでもない無意味な弁解と、「もう一度見たい、いやダメだ」という謎の葛藤をもたらした。
Nissyの黒い乳首を見るまいと視線をそらした先に、クレープ屋があった。コロッとした形に丸めたクレープを売っているあの店である。その店は柱群のど真ん中、Nissyの茶褐色に取り囲まれていた。
お姉さんは虚無を見つめながら、クレープを売っていた。彼女はもうすでにNissyの裸体に関してベテランになっていた。
そのまなざしが黒い乳首に惑わされることはない。
お姉さんは朝から晩まで、粛々とクレープを売り続けていたのだ。
Nissyの茶褐色に抱かれながら。
さくらももこの親子観について
さくらももこのエッセイ 『そういうふうにできている』
さくらももこが亡くなった。まるちゃんよりエッセイが好きだった。ブログを読んでいると結構そういう人がいて、なんとなくみんな文章がさくらももこっぽいから微笑ましくなってしまう。わたしもちょっと真似しているところがあるかもしれない。
さくらももこのエッセイは、最初はひーひー笑いながら読んでいたけど、すこし嫌になってしまった時期があった。なんだか文章から漂う庶民的なみみっちさや僻みっぽさが、同族嫌悪的な感情を刺激してくるので疲れてしまうのだ。それでも今こうして読み返すとやっぱりおもしろい。とくに『たいのおかしら』や『さるのこしかけ』が好きだ。この二冊では庶民的なみみっちさも僻みっぽさも、絶妙なスパイスになっていてカラッと笑える。
笑えるエッセイ本は数あれど、本気で雷に打たれたような表現に出会った一冊がある。『そういうふうにできている』である。
親子ってなに?
親子ってなんだろうと考えると止まらなくなる。親子について考えるとき、日本はとことん儒教的である。社会的に、親は敬うものであるとされている。親のほうでも「育ててやったんだから」と言ったり、親孝行を期待したりする。そこでは親はひとりの人間というよりは、「親」という大きな概念のようになっている。
「父の日」とか「母の日」に乗り気になれないのは、みんなが「父」とか「母」というなんだか大きな存在に対して一斉に感謝して品物を贈っているという状況が、なんだか異様だと思ってしまうからだ。
わたしが母を好きで尊敬しているのは、「母」だからではなくて「ゆきこ」として生きてきたそういう人間だからだ。それはとても幸せなことなのだと思う。わたしがこの世にポンと産み落とされて、最初に育てる役割をした「ゆきこ」という人間とたまたま相性が良かったということだ。結局親子関係といっても、人間関係なのだと思う。
逆にこの世には、親と限りなく相性が悪かったことにより、自分の生い立ちを呪いながら生きる人もいる。このような人たちが苦しいのは、「親は子を無条件に愛するものだ」ともっともらしく決めつけて言う人がいるからである。親も子も、ただの人間同士である。ただ子供の方が幼いうちは身体も知能も未発達で、社会的にも成熟しようがないので親に環境を整えてもらう必要があるというだけである。そういう役割を全うする親もいれば、子供に対して愛情がわかずに、すこしも世話をしない親もいる。もしくはそういう役割を過不足なく行うだけで、子供に対してさして愛情を抱いていない親だっている。
「親」は子供にたいして無条件に惜しみなく愛情を与える大きな存在だと思われているが、実際の親はただの人間で、子供を愛したり愛さなかったりする気まぐれで不確かな存在なのである。
さくらももこの子供への考え方
こんなふうに言うと、親子というものを悲観的に考えていると思われるかもしれない。でもそうは思っていない。さくらももこの言葉に出会ったからだ。何度読んでも、腑に落ちるのだ。
『そういうふうにできている』は、さくらももこが初めて子供を妊娠、出産したときのあれやこれやをおもしろおかしく、ときに哲学的につづった名エッセイである。このときのさくらももこの文章に説得力があるのは、生まれて来た赤ちゃんを見るなり盲目的な愛情が大爆発するんじゃなく、至極冷静だからだ。
あわてながら、私は子供に対する自分の愛情というものについても冷静に観察していた。この子に対して、まだ愛情らしき感情がワッと湧き起こってこないのは単に私に余裕がないだけであろうか。
私達は本能の中にプログラムされている種の存続という任務を忠実に遂行しているのだ。子供は誰から教わらなくとも乳を吸う手段を身につけており、私もこの生命を死守しようとしている。愛情とは違う。似ているが別モノだ。
いわゆるマタニティハイとは無縁である。さくらももこは、この赤ちゃんが自分の体のなかから生まれて来た不思議を静かにみつめ、これからの自分と子の関係性について真剣に考えている。さくらももこは大きな存在である「親」になる気は全くなくて、初めから人間対人間として子供に接しようと思っていたのだ。
さくらももこは子供が出てきた自分の身体のこともとくに特別なものだとは思っていないようだった。ただ、その子が地上に降り立つための通路に過ぎなかったと、そう言った。その子は母体の分身でもなんでもなく、一個の独立した魂をもつ存在であると言った。
もしかすると彼の魂は経験豊富で私より大人だったりするかもしれない。だがこの世では新参者だ。
”家族”という教室に”お腹”という通学路を通って転入生が来たようなものだ。遠い町から転入してきた彼を、クラスメイトの夫と私は歓迎し、今後仲良くしていこうと思う。彼が知らないことが教えてあげ、いろいろな体験を共にし楽しく過ごすであろう。お互いの絆は固く結ばれ、かけがえのないものになるとも思う。
だがお互いに一個の個体なのだ。
私は”親だから”という理由でこの小さな生命に対して特権的な圧力をかけたり不用意な言葉で傷つけたりするような事は決してしたくない。
この考え方に、今でもずっと共感している。自分に子供が生まれる想像をたまにして不安になるけど、このさくらももこの言葉を思い出すととても気持ちが楽になる。母親のことが大嫌いだったあの娘も、この部分を読んでもらったら「ほんとうにその通りだね」って言っていた。人の考え方は変わりやすいものだから、さくらももこさんが最期までこんな気持ちでいたかはわからないけど、この言葉はたくさんの人の心を救うと思う。
日を追って、子供との絆は深まり、もっともっとかけがえのない存在になる事は確実に予想されるが、それぞれの個体は各人のものでしかないという”距離”はこのままであると思われる。もっともその距離は、”オナラのできる間柄”であるという非常に近い距離であろうが。
わたしがおならをすると、空気清浄機より先に母のゆきこは「ン???」と言う。わたしもまたオナラのできる間柄のもとで、クラスメイトのような親にいろんなことを教わってきた。
たまには感謝を伝えたくて、まったく「母の日」でない日にゆきこに口紅を買って帰省した。母の日だよと渡すと、ぱぱぱっと口紅を塗って「ゆきこ、こんな良い口紅はじめて~」とバレエもどきの変なダンスを踊った。この自分のことを「お母さん」ではなくて「ゆきこ」と呼ぶのがうちの母の奇妙なところであり、個性である。
そんな母に、正しく感謝して向き合えたのはさくらももこの言葉のおかげだと思っている。
ご冥福をお祈りします。